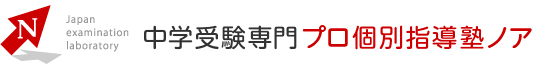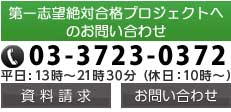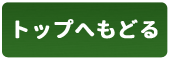平安時代その3 摂関政治と武士の台頭

今回は摂関政治を説明します。
摂関(せっかん)政治(せいじ)とは、藤原氏が自分の娘を天皇の妃にし、
その血縁関係を利用して政治の実権をにぎるしくみです。
摂関とは、摂政(せっしょう)・関白(かんぱく)を省略したもので、
どちらも天皇の政治を手助けする役職です。摂政と関白の違いがポイントです。
☆天皇が幼少(または女性)のときにおかれるのが → 摂政 です
☆天皇が成人してからおかれるのが → 関白 です
☆ここで初めてシリーズを3つ 日本で初めて摂政になったのは? → 聖徳太子 でしたね
藤原氏で初めて摂政になったのは? → 藤原良房(よしふさ) です
藤原氏で初めて関白になったのは? → 藤原基経(もとつね) です
摂関政治の全盛期は藤原道長(みちなが)・藤原頼通(よりみち)のときで、
藤原道長は自分の力の大きさを和歌にしたといわれています。
→ 「この世をば わが世とぞ思う(ふ) 望月の 欠けたることも なしと思え(へ)ば」
藤原頼通の時に男の子が生まれず、摂関政治は衰退していきます。
※道長と頼通の「みち」の字に注意してください。親子ですが、異なる字を使っています。
摂関政治は、藤原氏に都合がよいようにすすめられていきます。
都の政治が乱れれば、地方の政治も乱れます。
尾張国の国司、藤原元(もと)命(なが)の悪政を訴える文書が残っているように、
都から派遣された国司が好き勝手を始めます。
困ったのが、私有地(荘園)を広げていた領主たちです。
役人がしょっちゅう「税を納めろ‼!」と来るわけです。
そこで、領主は貴族や寺に荘園を寄進して所有者になってもらい、さまざまな特権を手に入れます。
☆特権は2つ覚えてください。
その1:税を納めなくてよい権利
→ 不輸(ふゆ)の権 といいます。
その2:役人の立ち入りを禁じる権利
→ 不入の権 といいます。
領主の中には「自分の身(土地)は自分で守る‼」と武装するものもいました。武士の登場です。
各地に点在していた武士がグループ化していきます。
→ このグループを 武士団 といいます。
武士団のトップを棟梁(とうりょう)といい、
清和(せいわ)源氏と桓(かん)武(む)平氏が有名です。
武士は朝廷に対して反乱を起こすほどに成長します。
☆武士の反乱も2つ覚えてください。
その1:<935年>平将門(たいらのまさかど)の乱 関東(茨城県)で反乱を起こす
その2:<937年>藤原(ふじわらの)純友(すみとも)の乱 瀬戸内海(愛媛県)で反乱を起こす
武士の反乱に対して、朝廷・貴族は何もできず、別の武士に依頼して解決してもらいます。
こうして、武士が政治の世界に進出していきます。
最後に、摂関政治のころに栄えた文化を国風文化といいます
(文化の名前では出題数ナンバーワンです)。
時代の名前がつかない文化の名前はよく書かせるので、きちんと覚えましょう。
文化史は覚えることが多く、キリがないですが、名前と特徴をまず覚えてください。
作品や作者を覚えるのはそのあとで構いません。
摂関政治は平安時代の大きなヤマですから、じっくり時間をかけて覚えていきましょう。
覚えるまで何度も動画を見てくださいね。
それでは、合格目指して頑張ろう‼