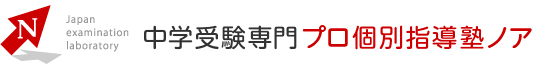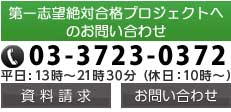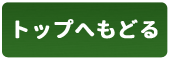ノア式予習シリーズ学習法 5年理科 地面や空気のあたたまり方

中学受験生のみなさん、こんにちは。
今回は、地面や空気のあたたまり方について解説していきたいと思います。
昼間に太陽から放射された熱は、空気をほとんどあたためずに地面をあたためます。
この熱は、地面からにげ出して空気中へと放射されます。
地面から放射される熱は、太陽の熱と違って空気をあたためます。
➀太陽高度と地面のあたたまり方
同じ量の太陽の熱が地面に当たっている時には、
太陽高度が低いと広い面積に、高いとせまい面積をあたためます。
地面を同じ面積にして考えると、太陽高度が低いと熱が少なくなり、
高いと多くなるということになります。
1日のうち、太陽が南中する時刻(正午)に地面は
太陽からの最も多くの熱を受け取っています。
➁地面の温度変化
昼間、地面は太陽から受けた熱を吸収してあたためっています。
しかし、それと同時に昼夜たえずに地面から空気中へと熱を放射しています。
このため、地面の温度は受ける熱と放射する熱の量の差で変化します。
日の出から午後1時ごろまでは地面の気温は上がり続けており、
太陽から受ける熱の方が地面からの放射熱より多くなります。
午後1時ごろは地面の温度が最高になり、
太陽から受ける熱と地面からの放射熱の量は等しくなります。
午後1時ごろから翌日の日の出までは地面の温度が下がっていくため、
太陽から受ける熱は地面からの放射熱を下回ります。
みなさん、地面や空気のあたたまり方についてしっかりと覚えましょう。