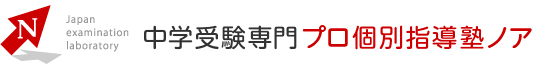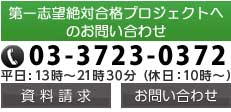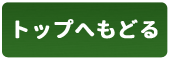ノア式予習シリーズ学習法 5年理科 昼と夜の長さの変化のしかた

中学受験生のみなさん、こんにちは。
今回は、昼と夜の長さの変化のしかたについて解説していきたいと思います。
地球は同じ向きに地じくがかたむいている状態で公転しているため、
太陽の光が当たる部分は毎日変化をしています。このため、昼と夜の長さは違っています。
➀春分の日
春分の日は、太陽が赤道の真上から照らしているため、
地球上のどの場所でも昼と夜の長さはほど12時間ずつになります。
➁夏至
夏至の日は、太陽が北回帰線(北緯23.4度)の真上から照らしているため、
北の地方ほど昼が長く、南の地方ほど昼が短くなります。
北緯66.6度以上の北極圏では、太陽が一日中しずみません。
赤道にある場所では、この日をふくめて一日中昼と夜がほぼ12時間ずつになります。
➂秋分の日
秋分の日も春分の日と同じように、太陽が赤道の真上から照らしています。
そのため、地球上のどの場所でも昼と夜の長さがほぼ同じになります。
秋分の日を過ぎると、日の出はさらに遅くなり、日の入りは早くなります。
➃冬至
冬至の日は、太陽が南回帰線(南緯23.4度)の真上から照らしています。
そのため、南の地方ほど昼が長く、北の地方ほど昼が短くなります。
みなさん、昼と夜の長さの変化のしかたについてしっかりと覚えましょう。